八話目
死んだはずの前妻が夜な夜な枕元に立つという男に襲いかかる怪異の話し
現代語訳:八 後妻打ちの話と法華経の力
武蔵国秩父の山里に、大山半之丞(おおやまはんのじょう)という男が住んでいた。ある日、彼が門の前に出ていたところ、諸国を巡る旅の僧侶が通りかかった。僧侶は半之丞を見てこう言った。

「あなたには女性の物の怪が憑いており、祟りをなすでしょう。命が尽きるのも近いようです。」
半之丞は驚き、「どうぞこちらにお入りください」と僧を奥に招き入れ、もてなしをした。そして、その後に半之丞は次のように話した。
「このような話をするのは恥ずかしいのですが、以前、私の妻が出産時に亡くなりました。そして最近、新しい妻を迎えたのですが、その亡くなった妻が夢なのか現実なのか分からない形で、毎晩枕元に現れて私を驚かせるのです。この障りをどのように祓えばよいでしょうか?」

僧はその話を聞き、「それならば、初めから物の怪があると見えていました。では封じましょう」と言い、半之丞を裸にさせて、彼の体に法華経の文を写経し、その後、亡妻の塚へ連れて行った。そしてこう諭した。
「どんなに恐ろしいことが起きても、決して怯えたり、息を荒げたりしてはいけません。」
僧侶はそう言い残して帰って行った。
その塚は人里離れた山中にあり、猿の哀れな叫び声がこだまし、鴟梟(ふくろう)の鳴き声が松や桂の木に響く、物凄い暗闇の中の夜だった。ちょうど村雨(にわか雨)が降り、夜も更けて五更(未明)に近づいた頃、亡妻の塚が少し割れ、その隙間から現れた。彼女は苦しそうに息をしながら、半之丞の上に腰を掛けた。さらに、二歳ほどの子供を連れており、その子供が塚の周りを這い回りながらこう言った。

「お父さんの足がここにあるよ。」
それは、半之丞が身にまとっていた荒菰(あらごも:荒縄のような衣服)が擦れて、写経した法華経の文が消えていた部分だったのだ。母親はそれを見て喜び、「これは足ではない、経木(お経を書くための木の板)だ」と言い、恐れて立ち去った。
その後、亡妻は左手に灯火を持ち、右手に子供を抱いて半之丞の家を目指して進んだ。家に近づく頃、灯火が消えた。それを見た半之丞は「また家に来て何か恐ろしいことが起こるのでは」と身を縮めて震えていた。

しばらくして、亡妻は新しい妻の首を持ち帰り、再び半之丞の上に腰を掛けた。そして子供に向かってこう語った。
「これでようやく父親を取り殺そうと思ったのに、どこかへ逃げてしまったようだ。今はここまでだ。長年の願いがようやく叶った。この女(新妻)は生前から私を調伏(退治)したので、死んでも炎の苦しみに耐えねばならなかったが、今こうして命を取ったことが嬉しい。」
そう言い残し、親子ともども塚の中に戻っていった。その頃、夜がほのかに明け始めていた。
このように、物の怪の祟りを鎮める法華経の力の物語として伝えられています。
所感
全身にお経を書いて邪をやり過ごすと言う話しは、「耳なし芳一」を思い浮かべますが、調べてみると「耳なし芳一」は、小泉八雲の『怪談』(1904年〈明治37年〉刊行)に所収の「耳無芳一の話(みみなしほういち の はなし)で広く知られるようになったとのこと。
典拠となったのは、江戸時代後期の天明2年(1782年)に刊行された一夕散人(いっせきさんじん)の怪談奇談集読本『臥遊奇談(がゆう きだん)』(全5巻5冊)の第2巻「琵琶秘曲泣幽霊(びわのひきょくゆうれいをなかしむ)」との事で、同じ時代に作成された話しだというのが分かります。
「耳なし芳一」と異なるのは、男は法力で助かるものの、前妻を陥れた後妻に復讐を果たす。
中々に後味の悪い話しではありますが、ストーリーの作りとしては夫も復讐対象ではあったけれども、実は後妻に元凶があった、と言う点でも軽いものですが、どんでん返しもありよく作られた話しだなと感じました。
参考書籍:
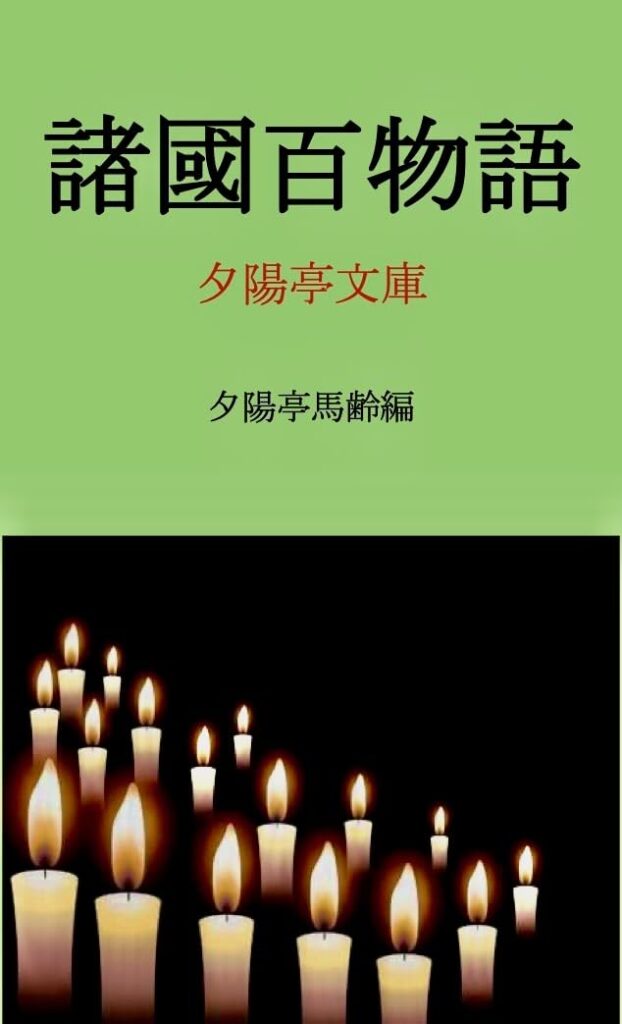
現代語訳ではないですが、ふりがなが振られており、単語の意味なども掲載されているので読みやすく勉強になります。

